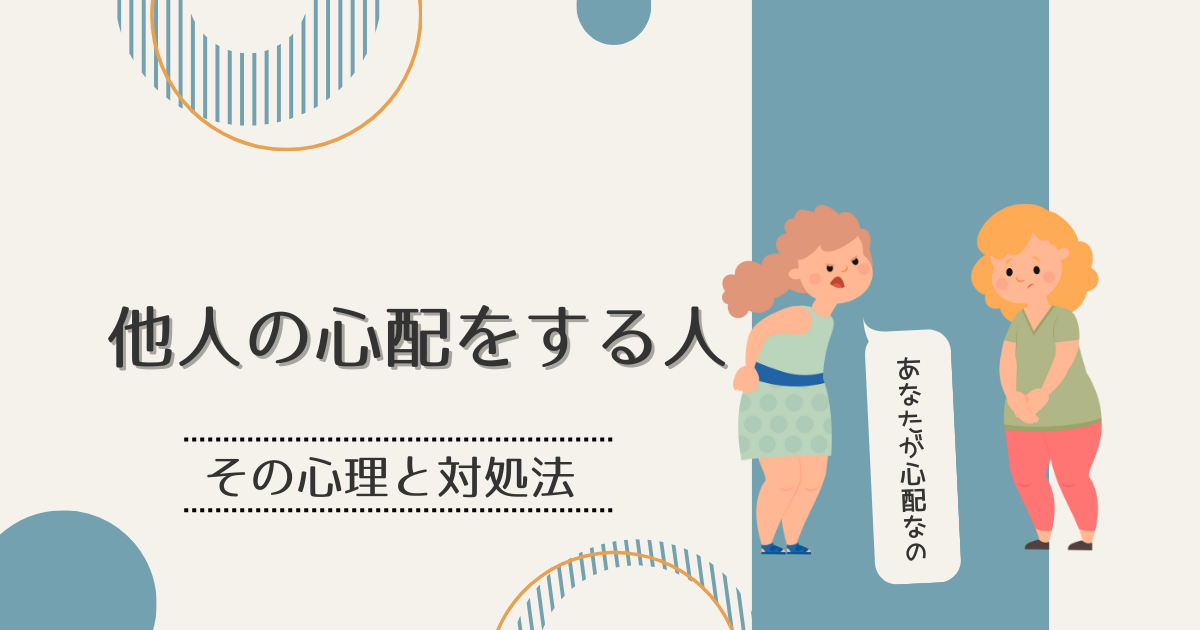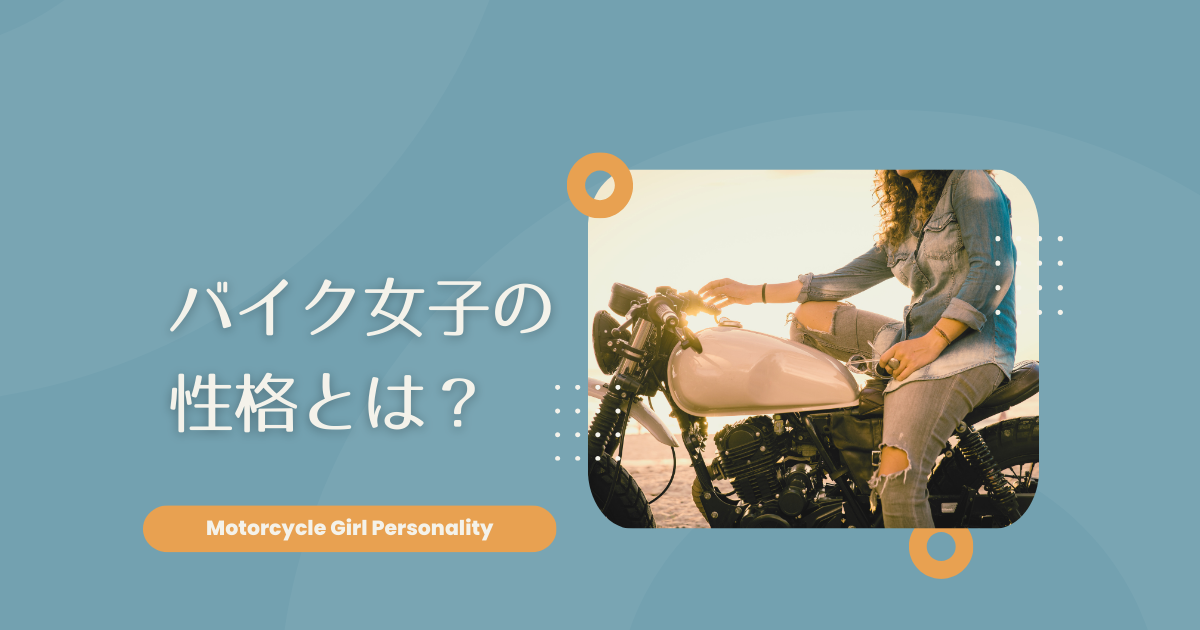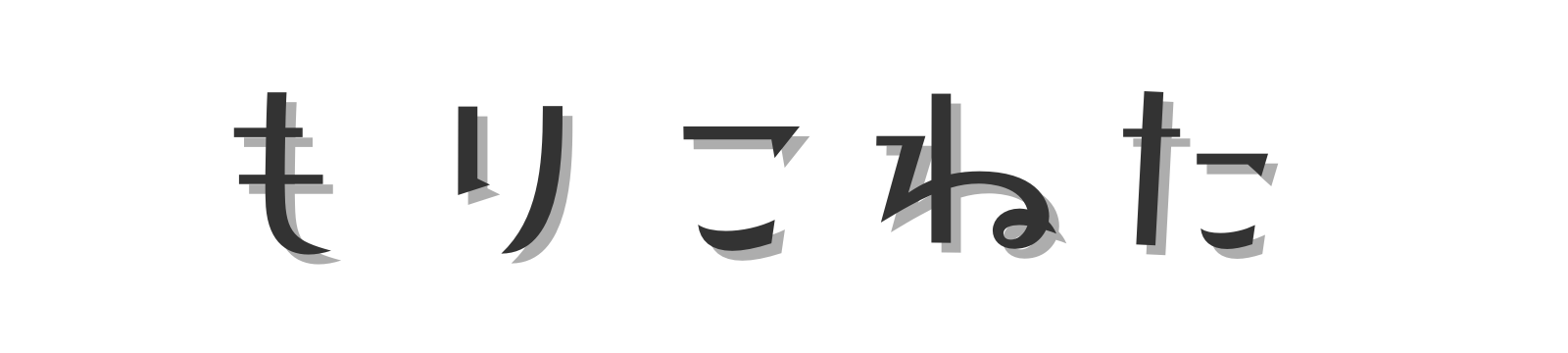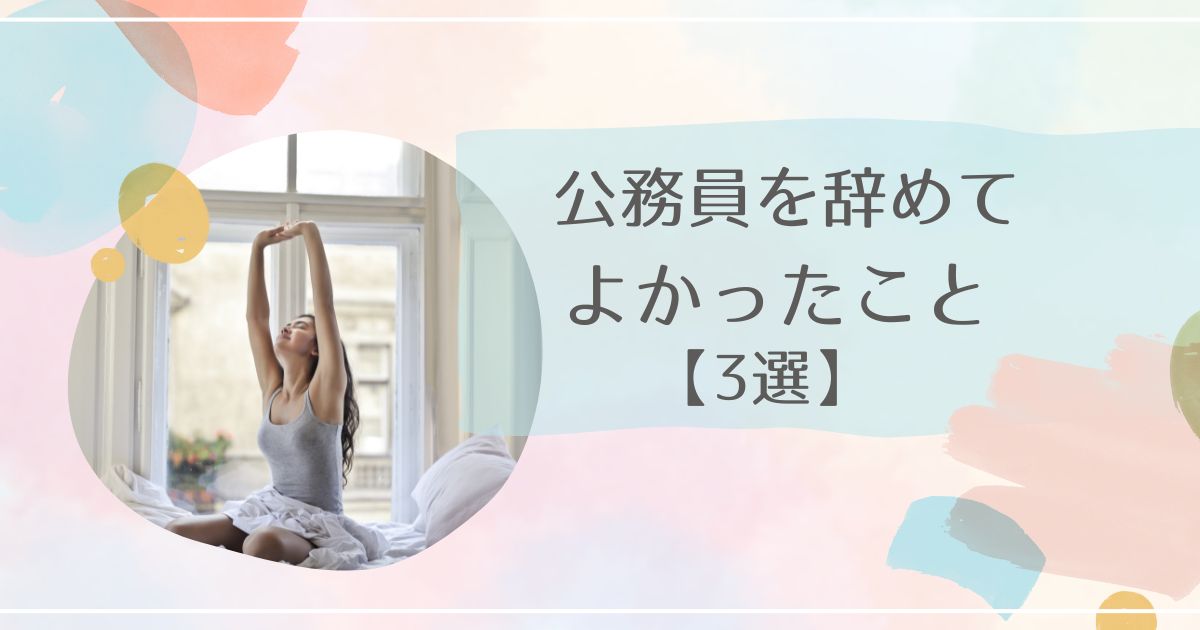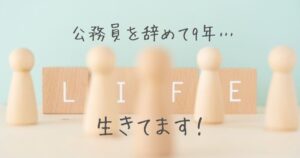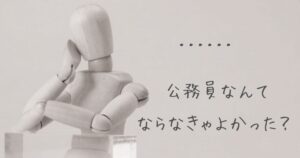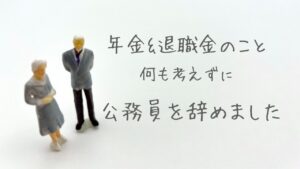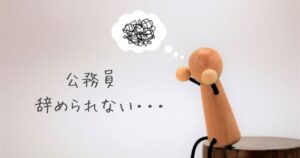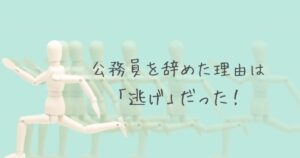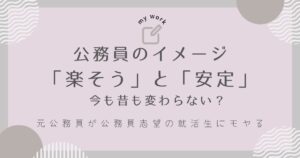以前、ある現役公務員の方から「公務員を辞めてよかったことって何ですか?」と聞かれたことがありました。
そこで、退職して10年以上経ちましたが、今一度「公務員を辞めてよかったこと」を整理し言語化していきたいと思い、今回このような記事を書くに至りました。
はじめに結論を申し上げますが、公務員を辞めてよかったことは、次の3つです。(注:個人の感想です)
- 公務員の副業は罪→働き方の選択肢が増えた
- 公務員の失敗はダメ。ゼッタイ。→失敗を恐れずトライできるようになった
- 公僕マインド→自分を大切にできるようになった
40代で公務員を退職したちょっと変わり者の私ではございますが、これらをひとつずつ説明していきます。
ただ、「公務員を辞めて公務員以上に稼げたぞ!」とか「公務員辞めてバラ色生活♪」という話とは真逆の、夢のない現実的な内容になることは否めませんので、参考程度にとどめておいた方が賢明です。
そして、勘のいい方はもうお気づきでしょうが、これらは別に公務員を辞めなくても「捉え方」によっては実現可能であるということです。
私の場合は、経験しないと気づけないウマシカ(馬鹿)人間なので、強行手段をとってしまったというだけの話ですので。
とはいっても、負け惜しみでも大げさでもなく、今は面白おかしく生きている公務員退職者の一人であることだけはたしかです。
注:かなりの長文です
公務員の副業は罪→働き方の選択肢が増えた
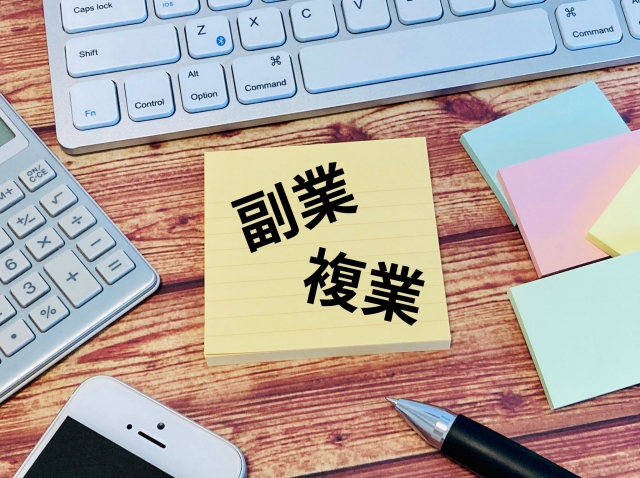
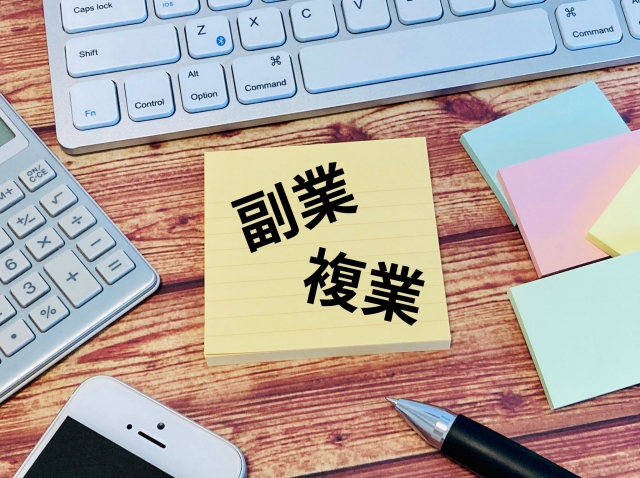
公務員時代と比べると、働き方の選択肢が増えたように感じています。
どういうことかといいますと、いわゆる副業やパラレルキャリア(複業)が実現しやすくなったということです。
公務員には、いわずとしれた「職務専念義務」があり、副業は基本できません。
正直、この義務に縛りを感じていた私は、公務員を辞めたことで、この見えない鎖から解き放たれ、あらためて「職業選択の自由♪」を実感したわけでございます(笑)。
ちなみに、私のしょぼい例で申し訳ありませんが、公務員を辞めた以降の副(複)業経験を挙げてみます。
最初の副業は、キャリアカウンセラーとして就職支援の仕事を本業にしながら、アロマテラピーの活動でわずかながらでも収入を得たことです。
現在は、やはりキャリアカウンセラーとして就職支援のプロジェクトに携わりつつ、個人でキャリア相談を開設しています。
また、当ブログを運営するとともに、最近ではとある企業の登録ライターとして活動をはじめました。
あと、これは単なる趣味になるのでしょうが、「自分の食べるものくらい自分で作りたい」と思い立ち、ど素人ながら狭いベランダで無肥料無農薬の野菜栽培に挑戦したり、半年間の農業体験もしています。
収穫を手伝ったことで、無肥料無農薬の美味しいお米もゲットできました。(労働の対価はお金ではなく食べ物です)↓


そして、これにより、次のようなメリットを体感しています。
- 副業等により複数の収入源を持つことが可能であるため、リスク分散できる
- 自分のできることややりたいことで、自分はもちろん人にも喜んでもらえる機会が増える
- 経験を積めるため、その分野のスキルや知識が高まる
- 人脈が増えることで、関連分野の情報が入手できたり、次の仕事のご縁にも恵まれる
これらのことにより、公務員時代は自虐的で自己肯定感が低かった私でも、少しずつ自分自身を信じられる(自信がつく)ようになってきました。
ただ、メリットがあれば、当然のことながらデメリットもあるのですよ。
- 複数の仕事をするには、ある程度の時間、体力、気力、精神力が必要
- 新たな仕事に携わる際は、自分の実力が問われるため、緊張感が否めない
- いくら自分が好きで始めたことであっても、決して楽しいことばかりではなく、嫌なことややりたくないことをしなければならなかったり、苦手な人との関わりも避けられない
- 収入面では、やる気や実力いかんによるが、公務員時代ほどアテにはできない(私の場合だけかもだが)
これを「不安定」と捉えるかどうかは、それこそ人によりけりでしょう。(といいますか大多数が不安定だと感じるでしょう)
ゆえに、すべての人にこの働き方をおすすめしているわけではありませんが、自分にはこの働き方、生き方が今のところは合っていると思っています。
しかし、これらは何も、公務員を辞めなくてもできることではないでしょうか。
副業については例外がありますし、パラレルキャリアに至っては、必ずしも収入を伴うものではありませんので、現役公務員でも十分実現可能です。
事実、現役公務員の中には、ブログやYouTube運営をはじめ、キャリア相談や講師活動をされている方をお見受けしますので、公務員のうちにできる範囲内で試してみるのもアリだと思います。
実は私、現役時代に、これら↓をやっておけばよかったなと、少し後悔しているのです。
- 公務員であったとしても、「自分ならどうする?」という個人事業主のような当事者意識(あくまで意識)で業務に携わること
- プライベートでは、自分が本気でやりたいことを、収入やら社会のニーズやらに囚われず、まずはとことんやってみる
とはいっても、言い訳がましいのですが、次から次へと押し寄せる仕事をこなさなければならないため、いちいち「自分ならどうする?」なんて考えるのは、現実的ではありません。
そして休日は、たまった家事をやっつけたり、身体を休めたり、気分転換に出かけたりで終わっていたので、私にとっては、現役中にこれらをやるのはなかなかに厳しかったのです。
公務員の失敗はダメ。ゼッタイ。→失敗を恐れずトライ!


公務員(公務の職場)というのは、「できて当たり前」を求められます。
失敗などしようものなら、「ダメ。ゼッタイ。」といわんばかりの体制であり、無駄に失敗に敏感な世界であると私は感じていました。
失敗が起こる原因というのは、往々にして「しくみ」の問題であると私は思っています。
それなのに、失敗の全責任を、失敗したその職員(担当者)に委ねてしまうという悲劇が起こるのが、公務の職場でございます。(上司は責任とりませんよ)
そんな環境で育ってきた私ではありますが、過去にこんな記事↓を挙げています。
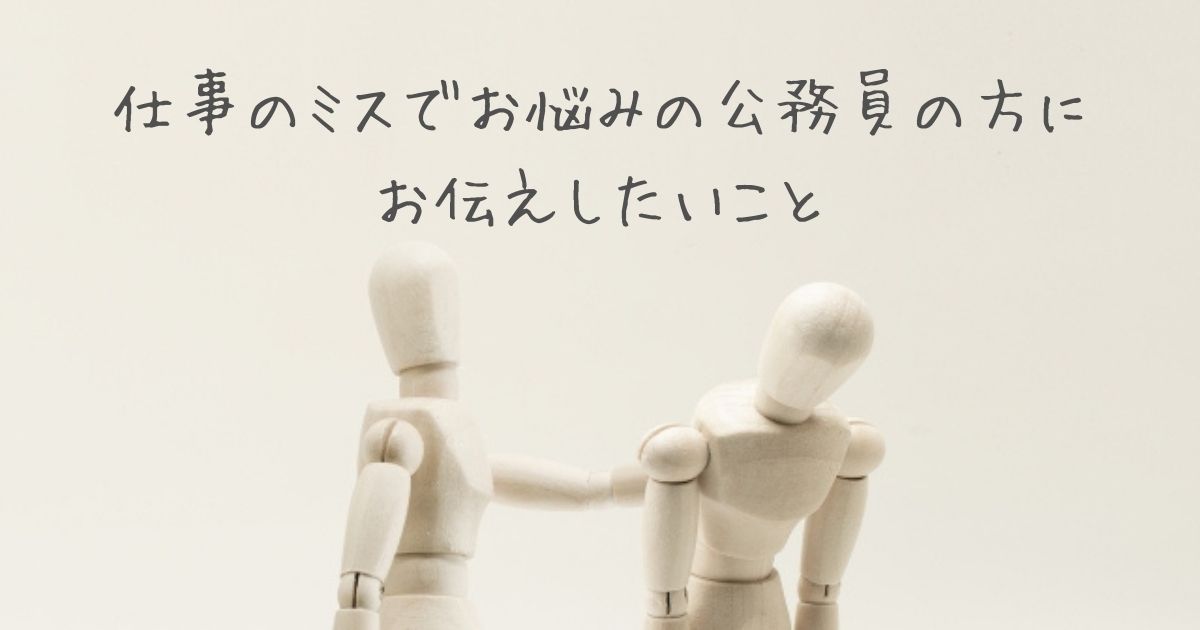
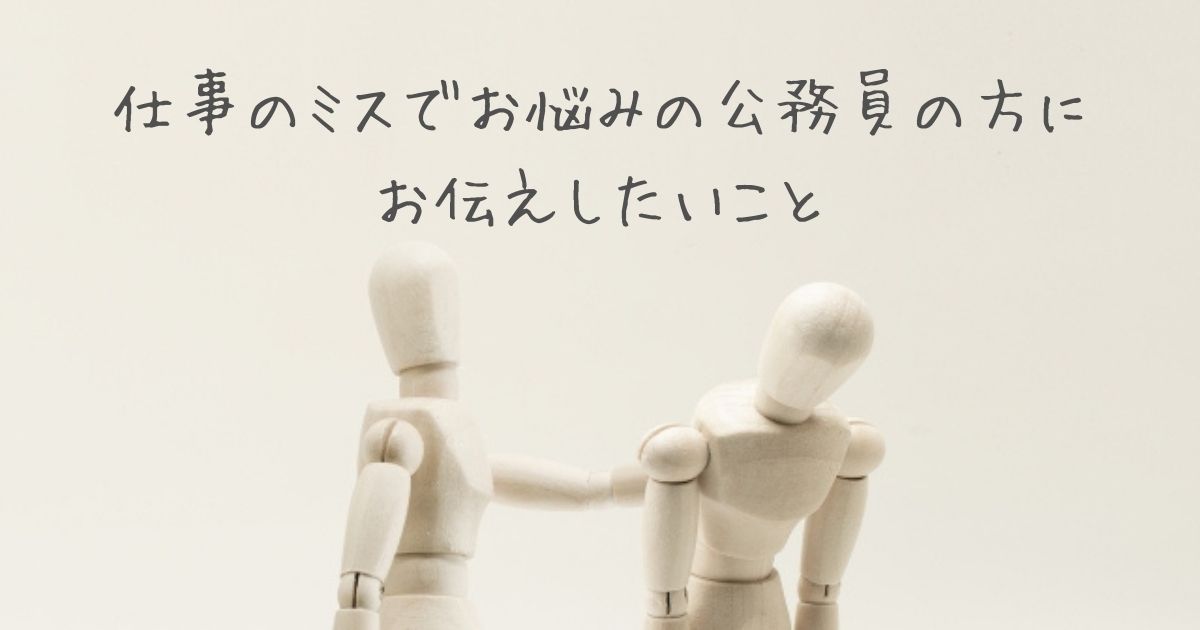
こんな私であっても、やはり「失敗しないこと」に注力して仕事をしていたことは否めないので、「失敗を恐れずトライしよう!」だなんて発想など、ほぼほぼありませんでした。
それよりも何よりも、失敗することは「無能」であり「恥」であると捉えていたのです。
ゆえに、失敗をした暁には、その事実を受け止められず、無意識にそれに目を背けていた(なかったことにしていた)ような気がするのです。(精神面においての話であり、現実的には失敗後の対応はしていましたよ、一応)
しかし、公務員を辞めてからの私は、さまざまな失敗経験の中で、「失敗しても命まで取られるわけではない」ということを体感し、少しずつ失敗に対する耐性がついてきたのです。
そして今は、失敗に対する捉え方が、こんなにエキセントリック(?)になってしまいました。
例えば、こんな感じです。
- 「失敗はただのフィードバック」と捉えられるようになったこと
- 「トライアンドエラー」の精神で、以前(公務員時代)よりも失敗をそれほど恐れなくなったこと
- 「まずはやってみる」ことで、自分に合うか合わないかが体感できたこと
- 失敗するたびに、「この経験はどこかの誰かの役に立てるかもしれない」と一人ほくそ笑み、場合によっては、それをこのブログで発信してしまうこと
- 大きな失敗や挫折経験のある人のことを、人間的魅力にあふれ信頼できる人であると思ってしまうこと(逆にそのような経験のない人に対して、今の私は一切魅力を感じない)
このような心境になったことで、生きるのがますます面白くなっています。
なので今は、状況が許すかぎり、やりたいと思ったことは、「できるできない」とか「損得」を基準とせず、お試し感覚でやってみることにしています。
とはいっても、こんなデメリットは否めません。
- トライの数だけ、失敗(と世間的にいわれるもの)は増える
- トライすることで、自分の無能さを目の当たりにし、他人からの厳しい評価に、凹んだり恥ずかしい思いをする時がある
- 時間やお金、労力を使う
それでも私は、経験に勝るものはないと思っている、懲りないやつなのです。
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」というビスマルクの格言でいえば、私は紛れもなく愚者にあたるのでしょう。
はい、それでいいのです。
「他者の失敗(歴史)から学びたい」と思われている賢者の皆様に対して、「はい!よろこんでーっ!!」と笑顔で経験談を提供させていただきたいと思っておりますっ!
そしてそんな私も、他者の経験から学ばせていただきたいという思いは、実は人一倍持っているのです。
そういえば、失敗について考察したこんな過去記事もありますので、よろしければどうぞ↓
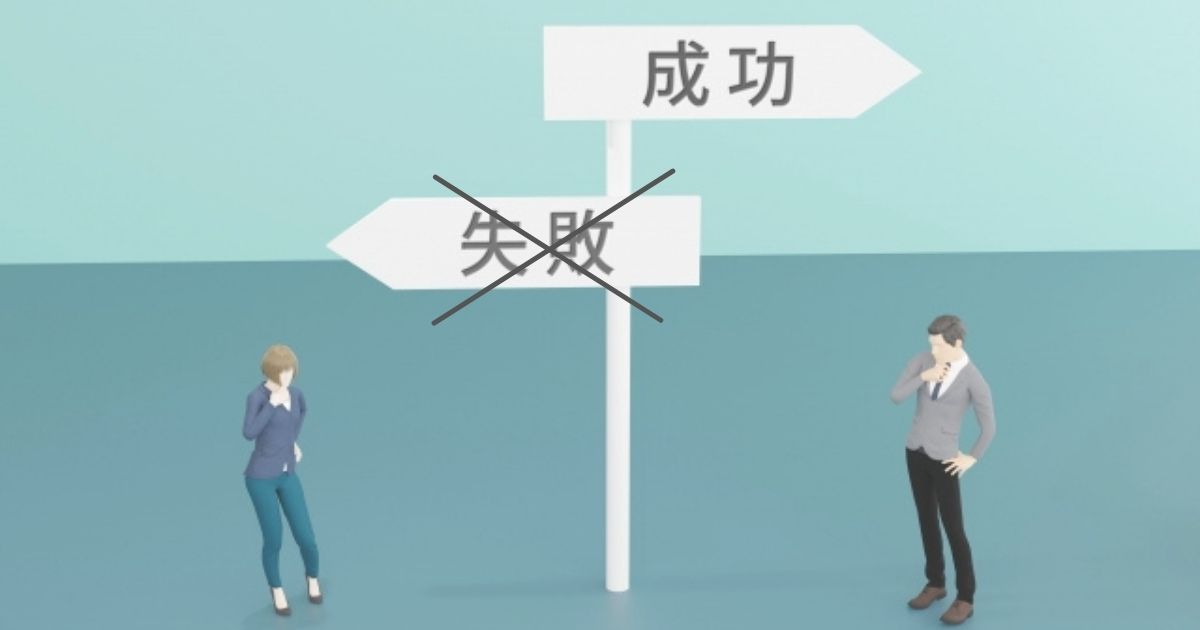
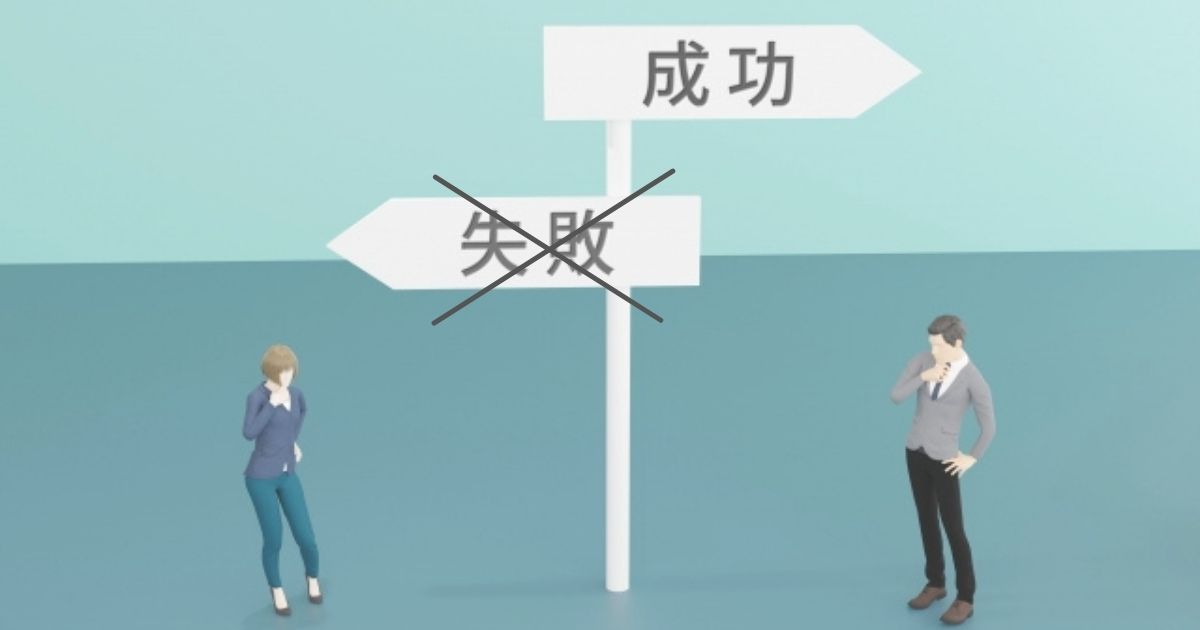
なんだかんだ語ってきましたが、失敗を恐れずトライすることは、公務員を辞めなくてもできることです。
公務員現役時代に、失敗について、もう少しこんなふうに捉えていればよかったなと思うことを、挙げていきます。
- 失敗をした際は、それから目を逸らさず、現実(事実)をきちんと受け止めること
- その失敗を、自分なりにフィードバックし、これからの人生に活かしていくこと
- 精一杯取り組んだ結果の失敗であれば、それは仕方のないことで、起こるべくして起こったことだと捉え、気持ちを切り替えること
- 失敗は無能でも恥なのでもなく、ただの経験と捉え、必要以上に他人の評価を気にしないこと
これらのことは、公務員を辞めなくてもできることばかりなので、辞めたのはそれこそ失敗だったのでしょうか???
いやいや、それも「おいしい経験」だと私は捉えていますよ。どこまでも懲りないやつなのです。
公僕マインド→自分を大切にできるようになった


これから書く内容は、おそらく自分のこれまでの「ドロドロした負の感情」を、他人が引いてしまうくらい吐き出すことになりそうです。
ゆえに、「こいつアタオカだ」「被害妄想が過ぎるやばいやつだ」と離脱されそうですが、それを覚悟の上でまとめていくことにします。
気分が悪くなられましたら、それは本当に離れてくださいませ。
さて、突然ですが、私は「公僕」という言葉が好きではありません。
公僕(こうぼく)
(「僕」はしもべ、召使の意)公衆に奉仕すべきものとして、役人、公務員をいう語
引用元:コトバンクより
少しおおげさな表現なのかもしれませんが、私はこの「公僕」という言葉に半ば洗脳され、自分を卑下してきたと言っても過言ではないと思っています。
言葉は人をつくりますので。
その公僕という言葉の影響なのか何なのか、公務員現役時代には、国民の皆様からこのような貴重なお言葉を頂戴したことがございました。
- 税金ドロボー
- 税金でメシ喰ってるくせに
- 上から目線で偉そう
- ぼーっとしてんじゃねーよ!
- 気楽でいいよねー
- よそ(民間企業)では生きていけない
- お前、馬鹿か?
- (税)金あるんだろ?こっちに払えよ!(←業界、間違ってませんか?)
さすがに私は「シネ!」といわれたことはありませんが、そういう経験をした職員もいるようないないような・・・
かの昔は、職員の事務机に、包丁を突き立て脅してきた来庁者も、いたとかいないとか・・・(あらヤダ奥さん〜)
そういえば、窓口で普通に対応していたのに暴言を吐かれ、メンタル不調→退職となった若手の女性職員が実際にいました。(上司のフォローはどうなってんだ???)
まあ、このような言葉を吐かれる背景には、こちら側にまったく落ち度がなかったとは、口が裂けても言えません。
でも、これはどうみても、どこにもはけ口のない不平不満をこちらにぶちかましているとしか思えないような言動もあり、稚拙だなと思いつつも、少なからず恐怖心も抱いていたのです。(だって・・・粗暴なんだもの〜)
そのような経験が、知らず知らずトラウマ(?)となっていたのでしょうか。
不自然にへりくだったり、妙な気遣いをしながら来庁者や電話に対応していたように記憶しているのです。
外側のせいばかりにするつもりは毛頭ございませんし、どう捉えるかもそれこそ自分しだいです。
それでも、仕事に対して自信が持てなかったり、自分を肯定できず邪険に扱ってきたようにも思うのです。
ちょっと何かにつまづくと、「自分なんて何にもできないダメ人間なんだ・・・」「自分なんて生きていく価値なんてないんだ・・・」などと、まるで子供にように拗ねたり、勝手に被害妄想して落ち込むなど、まあいい具合にめんどくさいやつでした。
そんな私でしたが、公務員を辞めてからというもの、ゆるやかに少しずつではありますが、「自分を大切にしていいんだ」ということに気づくことができています。
さらに、よくここまで生きてきたと、自分を認められるようになってきました。
そして、育ててくれた親や、関わってくれた周りに人たちに感謝ができる場面が増えたのです。
けっこう本気でそう思っているのですが、あまりこういうことを書くと、「いつか壺を売られるんじゃないか」と怪しまれそうなので、このへんでやめておきます。
それにしても、「公僕」という言葉、公務員を管理(支配)する側としては、なんて甘美な言葉なのでしょう。
そして、なんと都合のいい言葉なのでしょう。
公務員は国民の僕、すなわち自分たちよりも下の存在ということにしておけば、国や自治体に対する国民の不満を、そちらに逸らすことができる・・・可能性があるわけです。(あくまで可能性です)
この「公僕」という言葉に対し、なんの疑問も持たない人もいるのでしょうが、私は以前から違和感を抱いていました。
上も下もないでしょうし、偉そうにするのもへりくだるのも違うでしょう、と。
「そこまで考えなくてもいいんじゃない?」という声が聞こえてきそうですが、今ちょっとスイッチ入っちゃったんで、語らせてください。
例えばですね。
公務員はいまだに、「税金ドロボー」「税金でメシ喰ってる」などという、昭和から脈々と受け継がれる二大テッパン用語を日々浴びせられているわけです。(もうちょっと新しい言葉はないんですかね?進化がなくて面白くないでーす)
これに対し、窓口対応した公務員は、反論することが半ば許されず、ぐっと堪えながらも冷静に対応するしかないのです。
なにせ「国民の僕」ですし、関わるとめんどくさいというのが理由の一つなのですが、いくらくだらない言葉だと気にしないようにしていたとしても、それが日常茶飯事であれば、捻くれたり、自己肯定感が下がることは、否めないのではないでしょうか。
もし、そうならないのであれば、自分の感情を守るために蓋をしてしまったり、あまりにも日常的すぎて「たいしたことではない」と感覚が麻痺してしまっているのでしょう。(本当はそれ、めっちゃやばいと思うのですが・・・)
そもそも、「税金ドロボー」と言われましても、公務員の給料はたしかに税金から出ているものの、それは、「公益」のために「労働」した「対価」です。
大事なことだから、2回書きます。
「労働」の「対価」です
「働いて稼いだ銭」ですから、ドロボーではありません。
世間様からは、公務員は働いていないように見えるかもしれませんが、働いてますんで。
死に物狂いで働いてますんでー。(注:全員ではありませんが)
たしかに、非効率で無駄な仕事は多いです。でも、それは「しくみ」の問題であって、そこで働く公務員がすべて悪いわけではないのです。
むしろ、その「しくみ」に違和感や疑問、矛盾を抱きながらも、すぐには変えることができないジレンマと戦いながら、必死に仕事をこなしている職員も少なくなかったのですよ。
・・・おっといけない、今までの恨みつらみ(?)がバクレツ徹甲弾のようになってしまい、気がついたらこんな長文になっているではないですかっ。
で、結局何をいいたいのかといいますと、もし当時の私のように感じている公務員の方がいらっしゃれば、何よりも最優先すべきは、誰に何を言われどんな仕打ちを受けたとしても、「自分を大切にする」「自分を承認する」ということです。
大きなお世話は承知の上で申し上げますが、私のようになってほしくないからです。
最後に、公務員現役時代に、こんなふう↓に物事を捉えていれば、もう少し自分を大切にできたかなと思うことを挙げてみます。
- 職場の内外問わず、レベルの低すぎる暴言は、真正面から受け止めるに値する価値なし!時間の無駄!!
- とは言っても、その時抱いたネガティブな感情に蓋をしてはいけない(感情を麻痺させない)。「この野郎!」でも「ふざけんな!」でもなんでもいいので、一人の時にその率直な感情を感じ切り、吐き出す作業までしっかり行うこと
- 「公務員は偉そう」というクレームを回避するべく、必要以上にへりくだるのもどうかと。公務員は僕でも召使でもドロボーでもない。「対等な人間同士のやり取り」であるという思いで、恐れずに凛とした態度で臨むこと。
- 自己啓発系だスピ系だと侮ることなかれ。誰かに認められたいとか評価されたいとう外側に依存するのではなく、自分を信じ、頑張ってきた自分を認めること。自分を大切にしないと、他人からも大切にされない。
- 他人のせいにしたり、他人が何とかしてくれるなどと期待することほど無駄なものはない。自分の機嫌は自分でしかとれないし、自分の心と身体は自分でしか守れないと心得ること。
特に、感情に蓋をしたり麻痺をさせると、自分は本当はどうしたいのか、どう生きていきたいのかという自分の本心(羅針盤)がわからなくなってしまいます。
これらは、公務員時代の自分だけでなく、今の自分に対しても言いたいことなのです。
おわりに:人生は捉え方しだい?


公務員を辞めてよかったことを挙げてみましたが、最初に申し上げたとおり、「捉え方」しだいで、辞めなくてもできることばかりだったのではないでしょうか。
公務員を辞めることが良いのか悪いのか、正しいのか間違いなのかなんていうのは、身も蓋もないいい方ですが、やってみなければわからないし、その人しだいということしか、今の私にはいえません。
ただ、もし正解というものがあるのだとすれば、その時に自分が選択したことは、すべてが起こるべくして起こったことであり、自分にとってのベストだということです。
その選択について、悪いだとか間違いだとか失敗などとは、私にはどうしても思えないのです。
私たちがこの世に生まれてきたのには特に意味などなくて、ただ、さまざまな経験を通して喜怒哀楽の感情を味わうため・・・なんていう人がいますが、私も今のところはその考えに賛同しております。
ゆえに、私にとっては「公務員になった」という経験、「公務員を辞めた」という経験、そして、それらのおかげで、こうして「公務員記事を書ける」という経験、そのすべてが貴重なのです。
もしかしたら、「公務員を辞めずに続ける」という経験でも、貴重な経験として捉えられたかもしれません。
やはり人生は「自分の捉え方しだい」なのかもしれませんね。
はい、余計なおせっかいでした。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました!